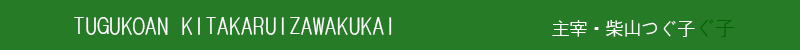ホームページ バックナンバー |

第210回 北軽井沢句会 (2022/6/8)
第二百十回銀漢北軽井沢句会会報 和四年六月八日(水) 管理事務所 兼題 当季雑詠五句 席題 梅雨寒 空木 |

photo by Udai 2022/6/5 撮影


嬬恋路。

嬬恋路。
| 子蟷螂の生命湧くごと飛び出せり 静かなる村に警報梅雨出水 咲きくれし一茶好みの九輪草 山藤の競ゐと四方明るうす |
柴山つぐ子  |
| 裏木戸の可憐な薔薇の紅競ふ 余生楽し十薬花の白浮けり 南風や耳より大きイヤリング |
小林 好子 |
| 幽谷は天狗の里や青林檎 卯の花や優しき母の嘘ひとつ 梅雨寒や丸太の椅子の傾きて |
佐藤 栄子 |
| 神話聴く千年杉の木下闇 万緑の湯の丸山の方位盤 手から手へ渡されてゐる落とし文 浅間嶺を離れぬ雲や梅雨寒し |
山﨑ちづ子 |
| 一寸を行きつ戻りつ水馬 水と花揺るる花びんの空木かな |
佐藤かずえ  |
| 青鷺のまつすぐに翔び谷戸暮るる どこにでもある時計塔桐の花 |
岡田 久男  |
| 隨神像留守の山門若葉風 ゆで卵つるんとむけて夏に入る 花うつぎ散歩の道を明るうす |
北川 京子 |
| 梅雨入りや夫婦で決めし農休み 豆蒔くや浅間のけむり濃く淡く 火の山の今朝も晴れなり山つつじ |
黒岩伊知朗 |
| 杉落葉傾ぐ階百余段 梅雨寒や高圧線の濡れ烏 卯の花のこぼるる谷に薄日さす |
黒岩 清子  |
| 栗の花匂へど子等や球を蹴る 梅雨湿り軋むペダルや駅舎へと |
佐々木終吉  |
| 薔薇の花成長ごとに色変化 稚児百合の図鑑で分かる群生地 |
佐藤さゆり  |
| |
|
| 田植時俄か賑はふ峡の里 四方より朝昼晩に時鳥 田の中に波立て泳ぐ太き蛇 |
白石 欽二 |
| 梅雨寒や煙たなびく山家かな 突然の雹の襲撃身を隠す |
武井 康弘  |
| 蝉しぐれ観音堂の大草鞋 ひめゆりてふ乙女散る島梯梧咲く 郭公や今朝も遺影に二、三言 梅雨寒や浅間は深い雲の中 |
中島みつる |
| 山藤の彩る谷間嬬恋路 五月雨や民家三軒無人駅 |
山﨑 伸次 |
| 梅雨入りと重なり合ふて今日の雨 句座の座に華やぎ香る花うつぎ |
横沢 宇内 |
★郭公が鳴いています。時鳥も始まりました。大自然の恵みを体いっぱい頂いています。 有難く感謝です。心さわやかに作句です。 (柴山つぐ子) ★七月の句会 七月十三日(水) 午後一時 管理事務所 兼題 甲虫 胡瓜もみ 釣忍 当季雑詠二句 ※七月より午後一時からとなります。お間違えのないように うめくさ 朝晩寒いですが爽やかな恵みの季節です。季節は梅雨ではありますが。 素のままに、地のままに、あるがままに素直になり作句に励みましょう。 きっと良い句が出来るでしょう。 季語は俳句の重要な約束ごとであることはいうまでもないことである。一句の中に季語を働かせるには、季語をよく知ることが肝要である。それも単に知っているというだけでは不十分で、その季語の持つ季節感や微妙なニュアンスを理解しておくべきである。そのためには歳時記を常時携帯して、いつでも見られるようにしたい。 (2022 6 12 つ) |

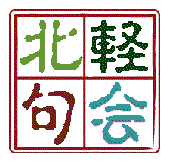 |
ホームページに戻る